大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で鎌倉が注目されている。鎌倉、源頼朝そして源氏。頼朝について知りたい。源氏とは何か。を突き詰めていくときに、源氏と北条氏が信奉した鶴岡八幡宮にたどり着く。一体鶴岡八幡宮とは何か。さらには、八幡宮とは何か。そのあたりを探ってみることにした。そうすることで、ドラマの背景を知り、より深く楽しめるのではないであろうか。

八幡宮とは
まず、八幡宮を見てみたい。現在全国にはこの八幡宮とつく神社が44000社あるといわれる。実に多い。稲荷神社と並ぶ多さではないだろうか。これほど八幡宮が全国に広がり、人々の生活に定着するには理由がなければならない。
この八幡宮の総本山が大分の宇佐にある宇佐八幡宮である。さらに鶴岡八幡宮が勧請されて作られた元の神宮は京都の石清水(いわしみず)八幡宮であった。これら宇佐八幡、石清水、そして鶴岡が八幡宮が日本三大八幡宮となっている。特に石清水八幡宮で源義家(頼義の子)が元服し、「八幡太郎」と呼ばれ、武家の中では武神として信仰し始めるようになっていった。
八幡宮が祭られている神はまず、応神天皇(誉田別命)である。応神天皇は弓術の天皇として記されているがゆえに、武家の神として認識されることとなる。そこから出世運の神とつながる。よって、八幡宮が日本社会に定着するゆえが、この武家の神と出世の神という点からうなずけるところがある。
その外に比売神、応神天皇の母である神功皇后が祭られている。
しかし、八幡神と言われる神は神話の記録のどこにもない。ここが大きな謎となっている。記紀などの記録もない神宮がここまで広がりを見せたのはなぜなのか。
ここには「八幡」という文字がカギを握る。それを探る前に、源氏との関係を見ていくことにしたい。
源氏と八幡
源氏と八幡の関係を見る上で、最も目につくのはもちろん鶴岡八幡宮であり、頼朝が戦勝祈願をしたという観点からみると、八幡と源氏は切っても切れない関係があることは推測できる。
さらに、河内源氏の系譜をみると、源氏の頭角を立てた、頼義の子、義家に注目したい。彼は元服をして「八幡太郎」と名付けている。
そして、興味深いのは彼の弟である義光(よしみつ)は三井寺の新羅善神堂で元服し「新羅三郎義光」となのっている。ここは「新羅明神」が祭られているのであるが、「新羅明神」は園城寺の開山、智証大師円珍が唐から帰途、船の中でこの新羅明神があらわれ彼のために仏法を守護すると誓ったという。
新羅と縁の深い神であることはわかる。
さて、八幡をこのように元服名につけるほど、何かしら八幡に愛着や信仰のようなものがあったことを伺うことができる。それは、義家の弟が新羅三郎を元服名につけていることをみると、新羅明神への何らかのよりどころがなければならない。八幡太郎も同じである。
源氏、特に頼朝の生涯や戦いをみると、どうも神がかりなところがあるように思われる。平治の乱で死を免れ、伊豆に流されたこと、一の谷の戦い、石橋山の戦いで敗れたものの富士川の戦いでの勝利など、どこか源氏には神かがっているところがある。
これは、もちろん平氏への各地での不満そして、西日本の飢饉、清盛の死などの悪条件も重なったことはたしかだが、源頼朝を始めとする、どこか武士の神への信仰のようなものがあってのことのような気がする。
それが「八幡神」ではないか。ここで、「八幡」について考えてみよう。
八幡と旗(はた)の関係
八幡の「旗」に関しては色々な説がある。
まず仏教徒結びつける説として、「灌頂幡(かんじょうばん)」がある。
次に神功皇后の遠征時に「千はた高はた」を置いて儀礼をおこなったとみる点である。「はた」を魂降ろしのための道具とみなすものである。
この2点から共通するものは。「幡」とは神の依り代であるということとなる。大和岩雄氏は『日本にあった朝鮮王国』の中で次のように指摘する。
”朝鮮がそと(蘇塗)という大きな木に鈴鼓をかけて、竿につけた紅旗のまわりに白紙・麻布・紅布を結びつけるような農旗と共通する。”という。
大和岩雄『日本にあった朝鮮王国』
 | 【中古】日本にあった朝鮮王国 謎の「秦王国」と古代信仰 新装版/白水社/大和岩雄(単行本) 価格:3,969円 |
八幡の八は八百万というときの「八」で多い問い解すことができる。よって、この大和氏の考察をもとにすると、
多くの旗ということとなり、その旗は民間信仰の五穀豊穣のための祈願であるといえよう。さらに、神の依り代という観点を合わせると、
旗に何らかの神霊を宿す神聖なものとみていたことがわかる。

『古事記』応神天皇の段にみえる天の日矛伝承がある。
新羅の国に一つの沼があって、そこに寝ていた女が日の虹に輝いていたところ、女は孕んで赤玉を生んだ。その赤玉を新羅の王の天の日矛が持ち帰ったというのであるが、彼は来朝して八種の神宝を奉斎した。そのうち浪振るヒレがあるが、これらも、旗と共通するものを感じられる。
そしてこれが仮に新羅の伝承と考えると、先の朝鮮の農旗に対する民間信仰と、この伝承が「朝鮮」というところでつながってくる。
天童思想
新羅には「花郎(ファラン)」という青年集団があった。これは、かれらが仏、または弥勒の化身とまで見られていたともいわれる。つまり、新羅では「天童思想」なるものがあり、童子を弥勒の化身のようにものとして、いわゆる”この世を救う童子”として捉える風習があったという。
「八幡」には神霊の降臨する依り代であるとみてきた。日本に渡来したこの神は、日本の神となった。そして日本においても、「幡」を祭る八幡神宮が勧請されていった。その中で、もっとも注目してきたのが、この「天童思想」ではなかっただろうか。
つまり、武士の誕生と共に、武家kウでは「武士の手本」となる童子のような存在、新羅での「花郎(ファラン)」のような存在を待ち望んだ。では「武士の手本」となる童子のような存在、新羅での「花郎(ファラン)」のような存在を待ち望んだ。
源氏の家系は清和源氏と言われるが、天皇家にそのルーツを求めると同時に、この「天童思想」が根強く脈々と受け継がれていったとは考えられないだろうか。
「八幡太郎」そして「新羅三郎」これらはどこか、「源氏」の家門を背負ってくれる存在として、自覚されまた期待されることの証であるように思われる。
そして、いよいよ源氏と平氏の一騎打ちの中で、源氏にその天童のような存在が現れる。
それが、「頼朝」であった。
彼は平氏打倒において、神がかりの戦いで、鎌倉幕府を築くのである。そこには、武神への信仰と同時に、「八幡神」への信頼、さらには、「天童」という自覚がなければなしとげられない偉業ではなかったであろうか。
頼朝の功績。この大河「鎌倉殿の13人」によって、もう一度源氏のルーツそして頼朝の思想を深く研究することが望まれている。
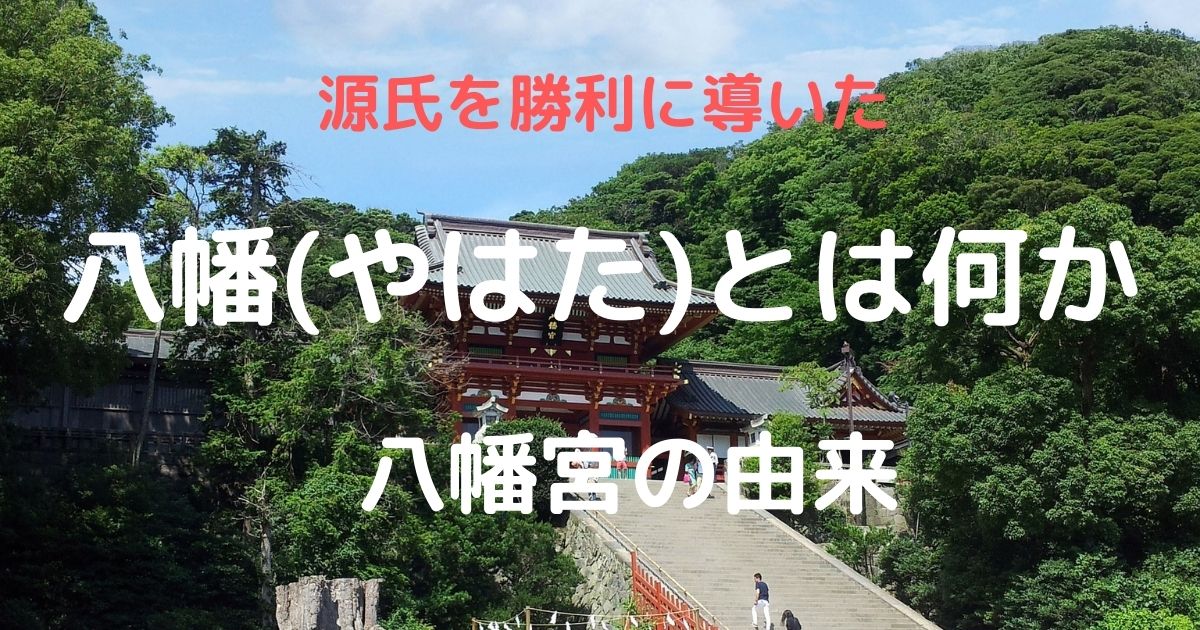

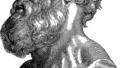
コメント